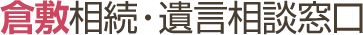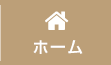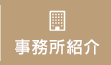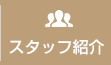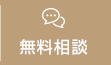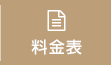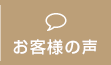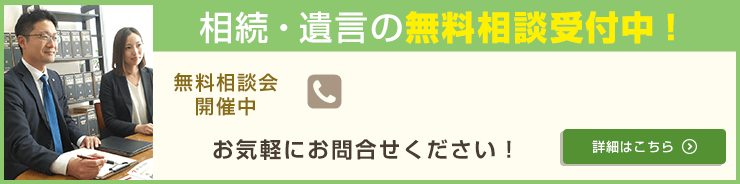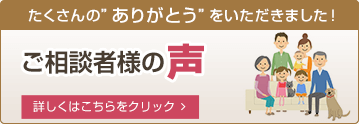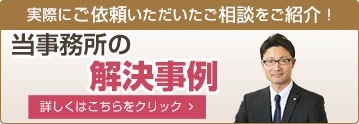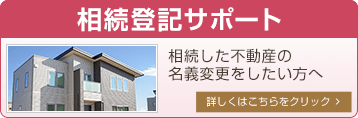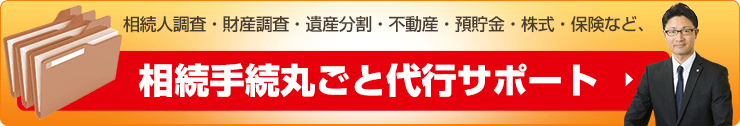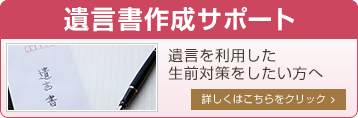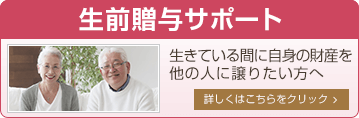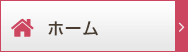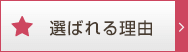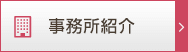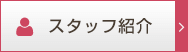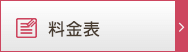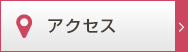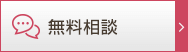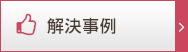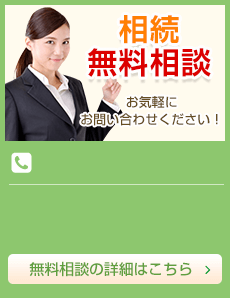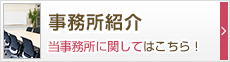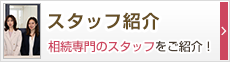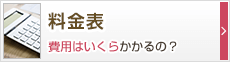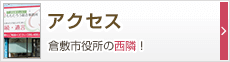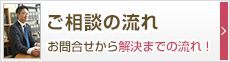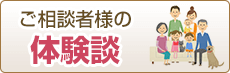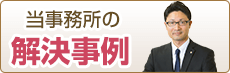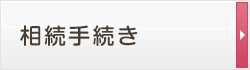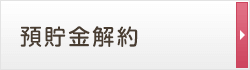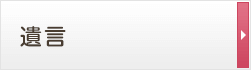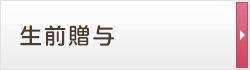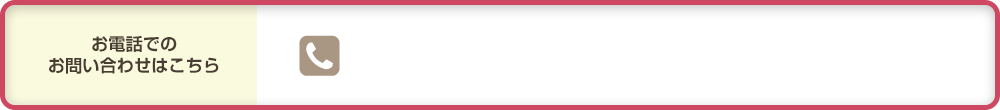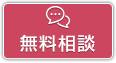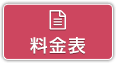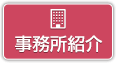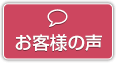異父兄弟が相続人にいたが、専門家に任せて無事に相続登記を完了した事例
ご相談者様の状況
ご相談者様
倉敷市にお住まいのAさん(77歳、女性)は、最愛の夫を亡くされた後、ご自宅の不動産の名義変更(相続登記)を行うため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
ご相談内容
Aさんご夫妻には子どもがおらず、当初は「自分と亡夫の妹であるBさんの2人が相続人」と思っていらっしゃいました。
ところが、戸籍調査を進めていく中で、思いもよらぬ事実が判明します。
亡夫の母親には再婚歴があり、その再婚相手との間に異父兄弟であるCさん(亡夫の兄)が存在していたのです。つまり、相続人はAさん、Bさん、そして新たに現れたCさんの3人であることが判明しました。
この事実にAさんは非常に驚かれました。
生前、夫からCさんの存在については聞かされておらず、まさか会ったこともない異父兄弟が相続人になるとは思ってもいなかったからです。
Aさんにとっては、突然現れた第三者にご自宅の相続手続きについて説明しなければならない状況が、精神的な負担となっていました。
実はAさん、以前に法務局に相談に行かれていたのですが、専門用語が多く、結局何をどうすれば良いのか分からないまま帰宅されたそうです。
そのため、「もう自分では手続きができない。すべてを専門家に任せたい」というお気持ちで、倉敷相続・遺言相談窓口を訪ねてこられたのでした。
相続手続きの設計
司法書士からのご提案内容
まず当事務所では、Aさんに対して現在の法的な相続人の状況と、手続きの全体像をわかりやすく説明しました。
今回のケースでは遺言が存在しなかったため、法定相続人全員の同意が必要となる「遺産分割協議書」を作成し、それに基づいて不動産の名義変更を行う必要があります。
そのため、Aさんご本人だけでなく、亡夫の妹であるBさん、そして新たに判明した異父兄弟のCさんにも連絡を取り、相続に関する協議に参加してもらわなければなりません。Aさんからは「Cさんと面識もないので、どのように話を切り出してよいかわからない」「相続分はきちんとお支払いするので、できるだけ穏便に進めたい」というご希望がありました。
そこで当事務所では、Cさんに相続の概要を説明するための文書を作成し、Cさんより連絡があったので直接出向いてお話をさせていただくことにしました。
司法書士は弁護士ではないため、相続の仲介や交渉を行うことはできませんが、手続きの説明や必要書類の準備についてはサポート可能です。
幸いなことに、Cさんも非常に理解のある方であり、「会ったことのない義弟の家を自分が相続するのは申し訳ない」とのことで、協議には快く応じてくださいました。
当事務所では、遺産分割協議書をはじめ、財産目録、不動産の詳細資料、相続関係説明図など、必要な書類をすべて整え、Cさん・Bさんの署名・押印を得て、無事に遺産分割が成立しました。
相続のご相談先に困ったら
| ご相談先 | 特徴や対応業務など |
| 司法書士 | 戸籍収集や不動産の相続登記、家庭裁判所での相続放棄など相続全般が対象。無料相談を行っている事務所も多い。 |
| 税理士 | 相続税申告、節税や減額方法、税務調査のリスク回避など相続税の課税対象者は必要。 |
| 弁護士 | 相続でもめた場合の和解交渉や訴訟相談、対策。 無料相談はほとんど行っておらず、紛争性がない場合は割高。 |
| 行政書士 | 相続人の調査はできるが、相続分野の対応範囲が狭い。 車の名義変更はできるが、不動産の名義変更はできない。 |
| 銀行 | 相続手続きの窓口になっても、自行の預金解約以外は提携先の士業が手続きを行うため、費用は最も割高。 |
| 市役所 | 公的機関なので心理的ハードルが低く、利用しやすい。 無料で相談できるが相談時間が短く、詳しい内容には不向き。 |
司法書士は、法律の専門家であり、不動産実務にも精通しています。
相続の対応範囲が広いので、最終的な手続きまで一貫した解決方法をご提示できます。
少しでも相続で困ったら司法書士による無料相談を利用することで、不安や疑問を解消し、心の負担を軽減できるかもしれません。
相続手続きを行うメリット
このように相続手続きの一切を専門家に任せることで、Aさんは大きな心理的負担から解放されました。
戸籍調査により意外な相続人が判明した場合でも、手続きを円滑に進めるための方法と流れを正確に案内できるのが、司法書士をはじめとする相続の専門家の強みです。
今回のような事例では、仮にCさんと連絡が取れなかったり、Cさんが協議に応じなかったりした場合、手続きは長期化し、家庭裁判所での調停などに発展する可能性もありました。そうなる前に、専門家が関わることで、適切な対応を迅速に取ることができたのです。
また、手続きの流れも明確でした。
まずは戸籍を取得し、相続人とその関係性を確定させ、被相続人の財産を洗い出して財産目録を作成。
その後、相続人全員の合意に基づく遺産分割協議書を作成し、不動産については名義変更(相続登記)を法務局に申請。すべての手続きが無事に完了しました。
さらにAさんは、この経験を通じて「自分に万が一のことがあったとき、残された親族が困らないようにしたい」と強く感じられたようで、後日、公正証書遺言を作成されました。
この遺言により、Aさんご自身の相続についても、あらかじめ明確な意思を示しておくことができたのです。
まとめ
事例の要約
今回の事例は、「子どものいない夫婦」にとって、相続人が思いがけず広がる可能性があることを示した、非常に象徴的なケースです。
特に近年は、再婚や離婚が珍しくなく、異父・異母兄弟が相続人として登場する事例も増えてきました。
Aさんは、ご自身ではどうにもならないと感じていた相続問題を、専門家に任せることでスムーズに解決できたことに、大変安堵されていました。
また、ご自分の将来の備えとして、遺言という選択肢を知り、実行されたことで、さらなる安心を手に入れることができました。
司法書士からのメッセージ
相続手続きは「誰が相続人か」を特定するだけでも、専門的な知識が必要です。
とくに親族関係が複雑な場合や、遺言が存在しない場合には、思わぬ人が相続人として登場することもあります。
そうした場合でも、司法書士や相続の専門家にご相談いただくことで、トラブルを未然に防ぎ、手続きを円滑に進めることが可能です。
「自分では無理かもしれない」と感じたときこそ、専門家の力を借りてみてください。
あなたの大切な財産を、安心して次の世代へ引き継ぐために、私たちが全力でサポートいたします。